 悩むプリセプター
悩むプリセプター「初めてプリセプターになったけど、何から教えればいいか分からない…」
「一生懸命教えてるつもりなのに、新人さんの反応が薄い気がする…私の指導、これで合ってるのかな?」
こんな悩みにお答えします!



初めまして、現役看護師+Webライターの「さくと」と申します。
新人看護師の指導、本当に悩みますよね。
僕は、とある病院で副看護師長をしながら、毎年やってくる新人さんの教育サポートをしています。
この記事では、10年以上新人看護師の教育に携わってきた僕の経験を踏まえて、以下のことをお伝えします!
- 多くの先輩が陥りがちな新人指導の「5つの罠」とその対策
- 新人の主体性と成長をぐんぐん引き出す「7つの秘訣」
- 忙しいプリセプターのための悩み解決Q&A
結論からお伝えすると、新人指導は、いくつかの大切な秘訣を知り、あなたらしい関わり方を見つけることで、必ずうまくいくようになります。
なぜなら、指導には普遍的なコツがあり、それは僕自身が10年以上の指導経験や研修、そして多くの指導者をサポートする中で確信してきたことだからです。この記事で紹介する方法は、決して特別なものではなく、意識すれば誰でも実践できることばかり。
毎日たくさんの業務を抱えながら、新人さんの指導計画を立てたり、日々の関わり方に悩んだり…。時間的にも精神的にも、いっぱいいっぱいになってしまうこともありますよね?
でも、安心してください。
この記事を読むことで、新人指導への漠然とした不安が具体的な行動に変わり、肩の力を抜いて、もっと自信をもって新人さんと向き合えるようになります。 そして、新人の成長はもちろん、あなた自身の成長にも繋がるはずです。
一緒に新人指導の悩みを解決し、あなたらしい指導スタイルを見つけましょう!
なぜ?経験を積んでも新人看護師の指導が「難しい」と感じる3つの理由と背景
経験を積んでも、新人看護師の指導が「難しい」と感じること、ありますよね。
僕自身、長く指導に関わってきましたが、今でも毎年新しい難しさや発見があります。決して、あなただけが感じていることではないんです。
では、なぜ経験豊富な看護師でさえ、新人指導に難しさを感じてしまうのでしょうか?
それには、主に3つの理由があると僕は考えています。
- 指導者(あなた)と新人との間にある「当たり前」のギャップ
- 日々の業務に追われる「時間的・精神的余裕のなさ」
- 「指導スキル」そのものを学ぶ機会の不足



一つずつ、具体的に見ていきましょう。
理由1:指導者と新人の「当たり前」のギャップ
まず、経験を重ねた僕たち指導者と、入職したばかりの新人さんとでは、「当たり前」と感じるレベルに大きなギャップがある、ということです。
僕たちは長年の経験で、たくさんの知識や技術、そして暗黙のルールなどを自然と身につけてきました。だからこそ、「これくらい知っているはず」「言わなくても分かるだろう」と、無意識に自分の「当たり前」を基準にしてしまいがち。僕も高校時代は人見知りで、看護の世界なんて全く知らなかったのに、いつの間にかその頃の気持ちを忘れてしまうんですよね…。
例えば、
- 病棟でよく使う略語の意味
- 物品の正確な場所
- 業務の優先順位のつけ方
- 医師や他職種との連携のタイミング
これらは、僕たちにとっては日常でも、新人さんにとっては未知の世界。僕たちが当然のように話している内容も、新人さんにはまるで外国語のように聞こえているかもしれません。



「経験があれば教えられるでしょ?」
そう思うかもしれませんが、自分の知識を分かりやすく伝える「教える技術」や、「相手の立場や知識レベルに合わせて考える」ことは、経験年数だけで自然に身につくものではないんです。
だからこそ、意識して新人さんの視点に立つ。これがまず大切です。
理由2:日々の業務に追われる「時間的・精神的余裕のなさ」
次に挙げられるのが、多くの看護師が抱える「余裕のなさ」です。これも大きな理由のひとつ。
日々の患者さんのケアはもちろん、記録、カンファレンス、委員会活動、時には緊急対応…。看護師の仕事は本当に多岐にわたります。そのうえ、慢性的な人員不足や業務量の多さを感じている職場も少なくないでしょう。僕の職場も、人員不足の中で新人指導をしてるので、重症患者さんがいたり、処置やケアが多い日は大忙しです。
そんな中で、プリセプターとして新人指導の役割も担うとなると、



「ゆっくり話を聞いてあげたいけど、時間が足りない…」
「ちゃんと指導計画を立てたいのに、後回しになってしまう…」
という状況に陥りやすいのではないでしょうか。
もちろん「忙しいのは皆同じ。その中でやるのが仕事だ」という意見もあるかもしれません。たしかに、時間の使い方を工夫する必要はあります。でも、構造的な問題からくる余裕のなさが、指導の質を低下させたり、何より指導する側の僕たち自身を疲弊させてしまったりする事実は、無視できないと僕は思うんです。
心に余裕がないと、どうしても指導が厳しくなったり、イライラしてしまったり…。そんな経験、ありませんか?
時間的・精神的な余裕のなさが、新人指導の難しさに直結している。これも現実です。
理由3:「指導スキル」そのものを学ぶ機会の不足
最後の理由は、僕たちが「指導のやり方」そのものを体系的に学ぶ機会が、実はあまり多くないということです。
多くの病院では、OJT(On-the-Job Training)といって、実際の業務を通して先輩が後輩に教える、という形が指導の中心になっていますよね。これは実践的なスキルを身につける上でとても重要です。
しかし、その「教え方」自体は、先輩から受け継いだ方法や、自分なりのやり方、つまり“見よう見まね”になっているケースが多いのではないでしょうか。
厚生労働省が示している「新人看護職員研修ガイドライン」では、体系的な研修プログラムの実施や、教育担当者の育成の重要性が述べられています(出典:厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン」)。
プリセプター研修などを実施している施設も増えましたが、その内容や時間は十分とは言えない場合も。僕自身も受講した実習指導者講習会のように、指導法を専門的に学べる機会もありますが、全員が受けているわけではありません。
つまり、「看護の知識・技術」と「それを効果的に教えるスキル」は別物なのに、後者をしっかり学ぶ機会が不足している。これも、新人指導を難しくさせている一因と言えるでしょう。



このように、新人指導が難しいと感じる背景には、個人の能力だけの問題ではなく、いくつかの構造的な理由が存在します。
まずはこの事実を知ることで、課題を客観的に捉えることができます。
そして、これらの理由に対する具体的な対策こそが、この記事でお伝えしていく「7つの秘訣」に繋がっていくんです。
【要注意】良かれと思って逆効果に?新人指導で“陥りがちな5つの罠”と具体的な対策
良かれと思ってやっている指導が、実は新人さんの成長を妨げる逆効果になっているとしたら…? ちょっとドキッとするかもしれませんね。



実は、多くの先輩たちが、知らず知らずのうちに陥ってしまいがちな「罠」というものが、新人指導にはあるんです。
僕自身も、過去を振り返れば「あれは失敗だったな…」と思い当たるフシがたくさんあります。
ここでは、僕がこれまでの経験で見てきた、特に注意したい「陥りがちな5つの罠」と、それぞれの具体的な対策についてお伝えしていきますね。
自分は大丈夫かな? とチェックするつもりで読んでみてください。
罠1:「これくらい分かるはず」指導 ~新人さんのレベル・理解度に合わせられない~
これは、経験年数を重ねるほど陥りやすい罠かもしれません。指導する側とされる側の「当たり前」のギャップからくるものです。
僕たちは経験を通して、専門用語や病棟のルール、仕事の進め方などを自然と身につけてきました。だから、「これくらい知ってるでしょ?」「この前教えたばかりだし」と、つい自分のレベルを基準に考えてしまいがち。
でも、新人さんにとっては、聞くことなすこと初めてだらけ。「〇〇しといて」と略語で指示を出したり、手順の一部を省略して説明したり…。良かれと思って効率を求めたつもりが、新人さんを「???」と混乱させてしまう。そんなこと、ありませんか?
意識して、指導者側が新人さんのレベルまで「下りる」こと。専門用語は分かりやすい言葉に言い換える、手順は省略せず一つひとつ丁寧に伝える。「何も知らない」という前提で接するくらいが、最初はちょうど良いかもしれません。根気が必要ですが、この丁寧さが後の成長に繋がります。



「どこまで下りたらいいかわからない」
という人もいるでしょう。そんな時は、“新人看護師”として対応するのではなく、“患者さんや家族”として対応するつもりで説明してみてください。病気や治療の説明をするのに、難しい医療用語を使用したり、説明を省略したりしないですよね?そんな意識で説明してみると伝わりやすいと思いますよ!
罠2:自分のペースで進める「一方通行」指導 ~新人さんの主体性と成長を尊重しない姿勢~
忙しい業務の中だと、つい指導者側のペースで物事を進めてしまいたくなりますよね。「マニュアル通りに、早く覚えてほしい!」そんな気持ちも分かります。
でも、指導の主役はあくまで新人さん自身。指導者が一方的に話し続けたり、質問する隙を与えなかったり、新人さんの意見や考えを聞かずに「こうしなさい」と進めたりするのは、成長の芽を摘んでしまう可能性があります。
「私の時はこうやって覚えたから」という成功体験が、必ずしも目の前の新人さんに当てはまるとは限りません。
指導のペースや方法は、新人さんに合わせて調整する意識を持ちましょう。「ここまでで何か質問ある?」「〇〇さんはどう思う?」と、こまめに立ち止まって確認したり、意見を求めたりする。時間は少しかかるかもしれませんが、新人さんが自分で考え、納得しながら進むことが大切なんです。



「聞いても新人さんが何も答えてくれないからわからない」
そんな時は、質問の仕方を工夫してみましょう!こちらは質問しているつもりでも“詰問”になっている。そんなこともあるかもしれません。質問の仕方については、この後で説明しますね!(秘訣2参照)
罠3:失敗を恐れすぎる「過保護」指導 ~具体的な実践・経験の機会を奪う~
新人さんに失敗させたくない、インシデントを起こさせたくない。その気持ち、すごくよく分かります。患者さんの安全を守る上で、当然の配慮ですよね。
ただ、その気持ちが強すぎるあまり、いつまでも簡単な業務しか任せなかったり、常に付きっきりで手を出してしまったり…。これでは、新人さんが自分で考えて実践する貴重な経験の機会を奪ってしまいます。
「失敗から学ぶことも大事っていうけど、やっぱり怖い…」そう感じるかもしれません。もちろん、患者さんの安全を脅かすような重大な失敗は絶対に避けなければなりません。
段階的な見守りを意識しましょう。最初は一緒に、次に「手は離すけど目は離さない」で見守る、そして大丈夫そうなら任せてみる。もちろん、いつでもフォローできる準備はしておく。この「任せる勇気」を持つことが、新人さんの自立心を育てます。(詳細は秘訣4で解説します)



「そんなことして新人さんがミスをしたらどうするの?責任取れない!」
指導者をしていると、新人のミスは自分の責任、と感じてしまいますよね。その責任感は大切だと思います。ですが、僕は新人さんに「安全にケガ(ミス)をさせてあげる」ことも大切だと考えています。守って守って一人前として送り出しても、自分でミスした経験がないと、後になって大きなミスをする。そういう新人さんを何度も見てきました。新人さんに責任感を芽生えさせるためにも、この視点をもって指導してみてください。もちろん、ミスした後のフォローは忘れずに!
罠4:「根拠は?」と問い詰める「丸投げ」指導 ~思考プロセスと知識の共有不足~
「根拠のある看護」はもちろん大切です。でも、新人さんに対して、いきなり「そのケアの根拠は?」「なんでそう考えたの?」と問い詰めてしまうのは、少し待ってください。
多くの場合、新人さんはまだ知識と実践が十分に結びついていません。そんな状態で根拠を問われても、答えられずに固まってしまったり、「また聞かれる…」と質問すること自体をためらったりする原因にもなりかねません。僕もプリセプターになったばかりの頃は、「自分で考えなきゃダメだ!」と思って、突き放すような聞き方をしてしまったことがありました…。
まずは、指導者自身が「思考発話」すること。「僕はこういう理由(根拠)で、こう判断して、このケアをしようと思うんだけど、どうかな?」と、自分の思考プロセスを口に出して見せてあげるんです。そうすることで、新人さんは「なるほど、こうやって考えればいいのか」と、知識と実践を結びつけるヒントを得られます。「思考発話」については後で詳しく解説しますね!(秘訣3参照)



「ずっとそんなことしてたらいつまでも新人さんが成長しない」
もちろん、いつまでもずっと思考発話を続ける必要はありません。ある程度思考発話を続け、「ここは前に思考発話してあげたところだな」と思ったら、新人さん自身にどう考えるか聞いてみてください。おそらく答えられる部分と答えられない部分があると思います。その時に、答えられなかった部分については改めて思考発話をしてあげる。これを繰り返していくことで少しずつ成長を促していきましょう!
罠5:関係構築を後回しにする「いきなり」指導 ~信頼なくして効果的な指導なし~
新しい環境で緊張している新人さんに対して、挨拶もそこそこに業務の指示を出したり、できていないことを厳しく指摘したり…。忙しいとついやってしまいがちですが、これも避けたい罠です。
どんなに正しい指導内容でも、相手との間に信頼関係がなければ、素直に受け止めてもらうのは難しいもの。むしろ、「怖い」「話しかけにくい」と思われてしまうと、報告・連絡・相談が滞り、かえってリスクを高めることにもなりかねません。
何よりもまず、新人さんとの信頼関係を築くことを最優先に考えましょう。笑顔で挨拶する、気さくに声をかける、小さなことでもできたことを認める(承認する)。安心できる、話しやすい、と思ってもらえる関係性(心理的安全性)を作ることが、効果的な指導の土台になります。(詳細は秘訣1で解説します)



「そんな悠長なこと言ってられない!仕事なんだから、まず業務を覚えてもらわないと困る!」
…たしかに、早く一人前になってほしい、業務をスムーズに進めたい、その気持ちはすごくよく分かります。僕も時間に追われているときは、つい焦ってしまうこともありますから。
でも、ちょっと考えてみてください。焦っていきなり指導を始めて、もし新人さんが心を閉ざしてしまったら…? 結局、指導内容はなかなか身につかないし、質問や報告もためらってしまうかもしれません。それって、かえって時間がかかったり、リスクを高めたりすることに繋がりませんか?
一見遠回りに見えても、最初に信頼関係を築くための少しの時間を大切にすること。 例えば、毎日の挨拶と笑顔、ちょっとした雑談(天気の話でも何でもOK!)、できたことへの「いいね!」の一言。そういった積み重ねが、実は一番の近道になることが多いんです。「急がば回れ」ですね。



これらの「5つの罠」、いかがでしたか?
「あ、自分もやってるかも…」と思ったものがあったとしても、落ち込む必要はありません。
多くの指導者が通る道ですし、大切なのは、まず「罠」の存在に気づくことです。
そして、それぞれの対策を少しずつ意識していくことで、あなたの指導は必ずより良いものになっていきます。
【実践編】新人の成長と主体性を引き出す!明日から使える「具体的な指導の秘訣7選」
さて、ここまで新人指導の難しさや、僕たちがつい陥ってしまいがちな「罠」について見てきました。
「やっぱり指導って難しいんだな…」と感じた人もいるかもしれません。
でも、ここからが本題の【実践編】です!
どうすれば、新人さんの成長と主体性を効果的に引き出すことができるのか?
そのための具体的な指導方法として、僕が日々の指導で大切にし、そして多くの後輩たちの成長を見てきた中で「これは効果がある!」と確信している「7つの秘訣」を、ここから一つひとつ紹介していきます。
難しく考える必要はありません。
ちょっとした意識の持ち方や、具体的な声かけ、関わり方のコツ。そんな、明日からでもすぐに実践できることばかりを集めました。
これらの秘訣は、単なる小手先のテクニックではありません。新人さんとの良好な関係を築き、その子らしい成長をサポートするための、いわば関わり方の土台となる考え方です。
この7つの秘訣を意識することで、
- 指導がスムーズに進みやすくなる
- 新人さんの「分からない」「できない」が「分かった!」「できた!」に変わる瞬間が増える
- 指導するあなたの負担やストレスも、きっと軽くなるはず
- そして何より、新人指導が「大変なもの」から「やりがいのある、楽しいもの」に変わっていく
そんな変化を感じてもらえるんじゃないかな、と僕は信じています。僕自身、これらの秘訣を意識するようになってから、指導がずいぶん楽になりましたし、何より後輩の成長を見るのがさらに楽しくなりましたからね。



それでは、さっそく一つ目の秘訣から、詳しく見ていきましょう!
秘訣1:【最優先】心理的安全性を土台に「信頼関係」を築くコミュニケーション術
7つの秘訣の中で、僕が【最優先】だと考えているのが、この「信頼関係」を築くことです。いきなり指導のテクニックの話じゃないの? と思うかもしれませんが、ちょっと待ってくださいね。
どんなに素晴らしい指導計画を立てても、どんなに効果的な教え方を知っていても、指導者と新人さんの間に信頼関係という土台がなければ、その効果は半減してしまいます。 下手したら、逆効果にだってなりかねないんです。
考えてみてください。新人さんは、慣れない環境、初めての業務、そして「先輩」という存在に、大きな不安や緊張を抱えていますよね。そんな時に、指導する先輩が「なんだか怖いな」「話しかけにくいな…」と感じる相手だったらどうでしょう?
きっと、「こんなこと聞いたら怒られるかな…」「失敗したらどうしよう…」と、分からないことを質問したり、困っていることを相談したりするのをためらってしまうはず。最悪の場合、ミスを隠してしまったり、一人で問題を抱え込んでしまったりするかもしれません。それは、新人さん本人はもちろん、患者さんにとっても、すごく危険なことですよね。
そこで何よりも大切になるのが、「心理的安全性」なんです。
これは、難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、要するに「この人の前では、何を言っても大丈夫だ」「分からないことを『分からない』と正直に言っても、頭ごなしに否定されたりしない」と、新人さんが安心して感じられる状態のこと。この“安心できる”という気持ちが、学びに向かう意欲や、素直に指導を受け入れる姿勢の、まさに土台になるんです。



「でも、そんな関係づくりに時間をかけていられないよ…」
忙しい毎日の中では、そう思う気持ちもよく分かります。でも、思い出してください。「急がば回れ」です。最初にこの信頼関係という土台をしっかりと作っておくことが、結果的に指導をスムーズに進め、新人さんの早期の成長に繋がり、ひいてはあなたの負担を減らすことにも繋がるんです。僕も、信頼関係ができてからの指導のしやすさを、何度も実感してきました。
では、具体的にどうすれば、心理的安全性の高い信頼関係を築けるのでしょうか?
そのための具体的な「コミュニケーション術」として、特に大切なポイントが次の3つあります。
- まずは「存在承認」から始めよう
- 「4つの承認」を意識的に使う
- 新人さんの考え・気持ちを引き出す「傾聴」
まずは小手先の指導テクニックよりも、新人さんが「この先輩は自分のことを気にかけてくれているんだな」「安心して関われるな」と感じられる関係づくり。ここが、効果的な指導の、そして新人さんの健やかな成長への、全てのスタート地点になります。
まずは「存在承認」から!新人看護師の不安を和らげる態度
では、信頼関係を築くための具体的なコミュニケーション術、その一番最初のステップは何だと思いますか?
僕がまず大切にしているのは、「存在承認」です。



「存在承認って、なんだか難しそう…」
と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。簡単に言うと、「あなたのことをちゃんと見ていますよ」「あなたがここにいることを歓迎していますよ」というメッセージを、態度や言葉で伝えることなんです。
考えてみてください。新人さんは、右も左も分からない新しい環境で、「自分はここでやっていけるだろうか…」「場違いじゃないかな…」なんて、大きな不安を感じているはず。僕自身、新人時代は結構人見知りで、病棟でいつもオドオドしていましたから、その気持ちはよく分かります。
そんな時、先輩から自分の存在をちゃんと認めてもらえている、と感じられたらどれだけホッとするでしょうか。この「ここにいても大丈夫なんだ」という安心感こそが、新人さんの心をほぐし、前向きな気持ちで仕事に取り組むための、本当に大切な第一歩になるんです。
じゃあ、具体的にどうすれば「存在承認」を伝えられるか?
特別なスキルなんて必要ありません。日々の基本的な関わり方がとても重要です。
(通りすがりにボソッと言うのではなく)できれば少し立ち止まって、相手の目を見て「〇〇さん、おはよう!」
「△△お願い」ではなく「〇〇さん、△△お願いできるかな?」
「〇〇さん、お疲れ様」「〇〇さん、大丈夫?」
「元気ないけど、どうかした?」「何か困ってることない?」
忙しくても、まずは「どうしたの?」と向き合う



「え、そんなの当たり前のことじゃない?」
そう思う人もいるかもしれませんね。自分の行動を振り返って、自信をもってそう言えるあなたは「存在承認」はバッチリ!でも、僕たちも日々の業務に追われていると、この「当たり前」がおろそかになってしまうこと、意外と多いのではないでしょうか。挨拶が流れ作業になったり、つい名前を呼び忘れたり…。
だからこそ、意識して、丁寧に、基本的な関わりを大切にする。
難しいテクニックよりも、まずはこの「存在承認」という種まきから。あなたの温かい態度が、新人さんの不安を和らげ、信頼関係という芽を育むための、大切な栄養になるはずです。
「4つの承認」を意識的に使う具体的な声かけ・態度
新人さんが少し安心感を覚えてくれたら、次のステップ。さらに信頼関係を深め、新人さんの「よし、頑張ろう!」という気持ちを引き出すために、僕がとても大切にしているのが「承認」です。
ただ、一口に「承認」と言っても、実はいくつかの種類があるんです。ここでは、特に意識的に使いたい代表的な「4つの承認」と、それぞれの具体的な声かけ・態度について紹介しますね。
このフレームワークを知っておくと、新人さんへの関わり方がぐっと具体的になりますよ。
【4つの承認の種類と具体例】
| 承認の種類 | 意味 | 具体的な声かけ・態度の例 |
|---|---|---|
| 1. 存在承認 | あなたが「いる」こと自体を認める | (前の項目でも触れましたが) ・「〇〇さん、おはよう!」(笑顔で目を見て) ・「今日もよろしくね!」 ・「〇〇さんがいてくれると助かるよ」 |
| 2. 行動承認 | 結果はともかく「やっていること」を認める | ・「忙しいのに、ちゃんと報告に来てくれてありがとうね」 ・「時間内に検温、頑張って回ろうとしてるね!」 ・「積極的に患者さんに声かけられていて、良いね!」 ・「苦手なことにも挑戦しようとしてるんだね」 |
| 3. 成果(結果)承認 | 「できたこと」「出した結果」を具体的に認める | ・「〇〇さん、点滴のルート確保、一回でできたんだ!すごい!」 ・「今日のケア、時間通りにきれいにできたね」 ・「患者さんが『〇〇さんの対応、丁寧だった』って喜んでたよ」 |
| 4. 成長承認 | 「以前と比べてできるようになったこと」を認める | ・「前は時間がかかっていた〇〇、すごくスムーズになったね!」 ・「最初は緊張してたけど、患者さんとの会話が自然になったんじゃない?」 ・「〇〇について、自分から質問してくれるようになって、僕も嬉しいよ」 |
これらの承認をバランス良く、そしてタイミングよく使うことが、とても大切なんです。
特に、まだ業務に慣れていない新人さんの時期は、「行動承認」を意識して多めに伝えてあげると良いと思います。たとえ結果が伴わなくても、「やろうとしていること」「頑張っているプロセス」を認めてもらえるだけで、新人さんは「ちゃんと見てくれているんだ」と安心できますし、次も頑張ろうと思えるもの。
そして、少しずつできることが増えてきたら、「成果承認」や「成長承認」を具体的に伝えてあげる。漠然と「すごいね!」と褒めるだけじゃなくて、「〇〇ができるようになったね!」「前より〇〇が早くなったね!」と、何がどう成長したのかを具体的に言葉にすることで、新人さんは自分の進歩を実感でき、さらにモチベーションが高まります。



「でも、そんなに褒めてばかりだと、調子に乗るんじゃない?」
「なんだか、わざとらしく思われそうで…」
そんな心配の声も聞こえてきそうですね。
大丈夫。「承認」は、根拠のないお世辞や、ただ甘やかすこととは違います。大切なのは、事実に基づいて、具体的に伝えること。 そして、心からの言葉で、真摯な態度で伝えることなんです。そうすれば、あなたの気持ちはきっと新人さんに届き、「認めてもらえている」という実感が、さらなる信頼関係に繋がっていくはずですよ。
新人さんの考え・気持ちを引き出す「傾聴」の実践方法
存在を承認し、具体的な行動や成長を認める「4つの承認」。これらとセットで、新人さんとの信頼関係をさらにグッと深めるために欠かせないコミュニケーション術があります。それが「傾聴」です。



「傾聴って、ただ話を聞くことでしょう?」
そう思うかもしれませんが、実はちょっと違うんです。傾聴は、単に耳で音を聞く(Hearing)のではなく、相手の“考え”や“気持ち”に、心と耳をしっかりと傾けて、深く理解しようと努めて聴く(Listening) 姿勢 のことを指します。
特に新人さんは、自分の意見を言ったり、困っていることを素直に表現したりするのがまだ苦手なことが多いですよね。「こんなこと言ったら、どう思われるかな…」なんて、不安でいっぱいかもしれません。
だからこそ、僕たち指導する側が、意識して「聴く」姿勢を示すことが、ものすごく重要なんです。
しっかりと自分の話に耳を傾けてもらえている、と感じることで新人さんは「この人になら話しても大丈夫かも」「私のことを分かろうとしてくれているんだな」と安心感を覚えます。
この安心感が、新人さんの考えを整理したり、気持ちを言葉にしたりすることを助け、結果として僕たちが新人さんの状況をより深く理解したり、悩みを早期に発見したりすることに繋がるんです。
では、具体的にどうすれば、相手の考えや気持ちを引き出す「傾聴」を実践できるのでしょうか? いくつか方法(ポイント)を挙げてみますね。
忙しくても、話しかけられたら少し作業の手を止めて、体を相手に向ける。目を見て穏やかな表情で。「あなたの話をちゃんと聞きますよ」というメッセージを、まず態度で伝えましょう。パソコン画面を見たまま、カルテを書きながら…といった「ながら聞き」は厳禁です。
「うんうん」「はい」「なるほど」「そうなんだね」といった相槌は、「ちゃんと聞いてますよ」というサイン。単調にならないように、バリエーションを持たせると良いですね。時々、相手の言葉を「〇〇だったんだね」と繰り返すのも、理解を示していることが伝わり効果的!
途中で「それは違うよ」「私の時はね…」なんて、自分の意見やアドバイスを言いたくなる気持ち、すごく分かります(僕も意識しているんですが、よくやってしまいがち…)。でも、そこをグッとこらえて!まずは、相手が話し終えるまで、口を挟まずに聴くことに徹しましょう。
「はい」か「いいえ」で終わってしまう質問(クローズドクエスチョン)だけでなく、「〇〇について、どう思った?」「どんなところが特に難しいと感じた?」「例えば、どんな状況だったの?」といった、相手が自由に答えられる質問(オープンクエスチョン)を投げかけることで、考えや気持ちが引き出しやすくなります。
会話の途中で、新人さんが黙ってしまうこと、ありますよね。あれ、不安になりませんか?でも、その沈黙は言葉を探していたり、考えを巡らせていたりする大切な時間かもしれません。焦ってこちらから言葉を挟まず、少し待ってみる勇気も時には必要なんです。
すぐに「こうすればいいよ」とアドバイスしたり、「それはダメだよ」と評価したりするのではなく、まずは「そう感じたんだね」「大変だったね」と、相手の気持ちに寄り添い、共感的に受け止めることが大切。アドバイスは、相手が求めてきたり、十分に話を聴いた後で必要だと判断したりした場合に、提案という形で伝えるのが良いでしょう。これも僕は意識しないとやってしまいがち…。



「でも、新人さんが全然話してくれないんだけど…」
そんな時は、もしかしたらまだ安心して話せる関係性ができていないのかもしれません。まずは、これまでに紹介した「存在承認」や「行動承認」を意識して、安心できる雰囲気づくりから始めてみてください。そして、焦らず待つ姿勢も大切です。



「忙しくて、そんなにじっくり聞いてる時間はないよ!」
その気持ちも痛いほど分かります。でも、傾聴は時間の長さだけではありません。例えば、業務報告を受ける短い時間でも、「聞く姿勢」を意識するだけで新人さんの感じ方は全く違ってくるはず。5分でもいいんです。その時間はしっかり相手に向き合う。その積み重ねが信頼を育みます。
この「傾聴」という実践方法は、新人さんの考えや気持ちを丁寧に引き出すための、そして、深い信頼関係を築くための、本当に強力なツールです。ぜひ、日々の関わりの中で意識してみてくださいね。
秘訣2:【質問力】「詰問」ではなく「発問」で新人看護師の思考力を育む
秘訣の2つ目は、新人さんの思考力を育む上で、とても大切な「質問力」についてです。
信頼関係の土台ができてきたら、次は適切な質問を通して新人さんが自分で考え、学びを深めていくサポートをしていきたいですよね。
ただ、ここで注意したいのが、僕たち指導者が良かれと思って投げかける質問が、意図せず相手を追い詰める「詰問(きつもん)」になってしまうケースです。
例えば…
「なんで報告しなかったの?」
「どうしてそんなことも分からないの?」
「前にも同じこと言ったよね?」
こういう詰問は、新人さんを「責められている」と感じさせ、萎縮させてしまいます。頭が真っ白になって、本来なら答えられるはずのことまで答えられなくなったり、「また怒られる…」と質問すること自体を恐れるようになったり…。これでは、思考力を育むどころか、考える意欲そのものを奪いかねません。



もっと最悪なのが、本来患者さんに向かないといけない意識が、指導者に怒られないように、というところに向いてしまうところ。
これでは、仕事にならないどころか、ミスにも繋がってしまいます。
そしてまた詰問されて…。最悪の循環ですよね。
そこで意識したいのが、「詰問」ではなく「発問(はつもん)」です。
発問とは、相手に考えさせ、答えや気づきを内側から引き出すことを目的とした肯定的な問いかけのこと。新人さんが自分の頭で考え、主体的に学びを深めていくための、いわば“考えるエンジン”をかけるスイッチのようなものです。
僕たち指導者の役割は、常に答えを教えることだけではありません(教えたくなっちゃうんですが…)。時には、新人さんが自分で答えにたどり着けるように、考えるプロセスをサポートすることが本当の成長に繋がるんです。
では、具体的にどんな問いかけが「発問」になるのでしょうか? いくつかポイントを挙げてみます。
- 詰問:「なんで失敗したの?」
- 発問:「どうすれば次はうまくできそうかな?」「〇〇を改善するには、どうしたらいいと思う?」
原因追求も必要ですが、未来に向けた建設的な問いかけが、前向きな思考を促します。
- 「〇〇さんは、この状況をどう思う?」
- 「他に何か方法は考えられそうかな?」
- 「今、どんなことを感じてる?」
答えを決めつけず、相手の視点やアイデアを尊重する姿勢が大切です。
- 「その時、患者さんはどんな様子だった?」
- 「判断するために、どんな情報があればよかったと思う?」
漠然とした状況ではなく、具体的な事実に焦点を当てることで、考えが整理されやすくなります。
最初から「根拠は?」のような難しい質問ではなく、「まず何から始めるのが良いと思う?」といった、答えやすい質問から始めてみましょう。少しずつステップアップしていくイメージです。



「考えてほしいから、つい厳しく問い詰めてしまうんだよね…」
その気持ちも分かります。でも、「考えるきっかけを与える」ことと「精神的に追い詰める」ことは全く別物。目的はあくまで、新人さんの思考力を育むことですよね。問い詰めるよりも、「一緒に考えてみようか」というスタンスで関わる方が、結果的に新人さんは安心して考えを巡らせることができます。



「どうやって発問すればいいか、具体的に分からない…」
そんな時は、まずはシンプルに「〇〇さんはどう思う?」と聞いてみることから始めてみてください。もし新人さんがすぐに答えられなくても、責めずに待ってあげる(沈黙も大切!)、あるいは次の秘訣で紹介する「思考発話」でヒントを出してあげる、という関わり方もできますよ。
この「詰問」ではなく「発問」を意識的に使う質問力は、新人看護師の思考力を効果的に育むための、指導者にとって本当に重要なスキルです。ぜひ、日々の声かけの中で、少しずつ意識してみてくださいね。



あ、最後に注意!
質問内容は発問でも、声のトーンや表情、態度で新人さんが「詰問」と感じてしまっては意味がありません。
話すときの自分の見え方にも意識を向けてくださいね。
せっかくの発問が台無しになっては、お互いにデメリットしかありませんから。
秘訣3:【教え方】具体的な思考プロセスを「思考発話」で見せる効果的な指導
秘訣の3つ目は、具体的な「教え方」のコツについてです。
先ほどの『陥りがちな罠』のところ(罠4:「根拠は?」と問い詰める「丸投げ」指導)でも少し触れましたが、特に僕が効果的だと感じている指導法、それが「思考発話(しこうはつわ)」です。
「罠4」の対策としてもお伝えしたように、いきなり「根拠は?」と新人さんに問う前に、まず僕たち指導者が「僕はこう考えているよ」という思考プロセスを口に出して見せてあげる、いわば「考え方のモデル」を示すことが、新人さんの学びにとってすごく大切なんです。
ここでは、その「思考発話」について、もう少し詳しく、具体的な実践方法や効果について見ていきましょう。



「思考発話って、具体的にどうやるの?」
これは、指導者である僕たちが、看護ケアやアセスメントを行う際に、頭の中で考えていること(思考プロセス)を、そのまま声に出して、いわば実況中継のように説明すること。「考えながら話す」イメージです。
なぜこれが効果的なのか?
新人さんは、教科書で知識は学んできても、それを実際の患者さんを前にどう使えばいいのか、最初は戸惑うもの。先輩が思考プロセスを見せることで、
- バラバラだった知識が、目の前の状況やケアと具体的に結びつく
- 看護師のアセスメントや判断の流れをリアルに学べる
- 結果として、看護実践能力、特にアセスメント能力の基礎が育まれる
という大きなメリットがあります。これは座学だけでは難しく、OJTだからこそできる非常に価値のある教え方なんです。
では、具体的にどうやって「思考発話」を実践すれば良いのでしょうか? いくつかポイントを挙げてみます。
例えば、患者さんの清拭を一緒に行いながら、「〇〇さんの皮膚は乾燥しやすいから、石鹸は使いすぎないようにして、保湿剤をしっかり塗るね。褥瘡予防のためにも、特に骨が出っ張っているところは優しく洗って、圧迫を避けるように体位も工夫しようか。なぜなら、〇〇のリスクがあるからね…」というように、一つひとつのケアの根拠や注意点を、考えながら声に出して伝えます。
バイタルサイン測定後などに、「熱が38.0℃あるね。脈も100回/分で少し速いかな。昨日より口唇も乾燥してるみたいだし、発汗もあるから、脱水のリスクも考えないといけないね。だから、まずは水分補給を促して、クーリングも検討しようか。この後、〇〇先生にも報告が必要だと思うんだけど、〇〇さんはどう思う?」といった具合に、観察した情報から、どう解釈し、どう判断し、どう行動しようと考えているのか、その流れを具体的に言葉にします。
ただ手順や判断を言うだけでなく、「なぜなら~だから」「こういうリスクがあるから」と、その思考に至った根拠(解剖生理の知識、病態生理、看護理論、あるいは経験則など)もセットで伝えることが大切です。
一方的に指導者が話し続けるのではなく、「ここまでのところで、何か気づいたことある?」「〇〇さんはどう考える?」と途中で問いかけ、新人さんの思考も促すことで、より深い学びにつながります。



「えー、ケアしながら全部説明するなんて大変だよ…」
「ずっとそんなことしてたら、自分で考えなくなっちゃうんじゃない?」
罠4でも触れましたが、常にすべてのケアで思考発話を完璧にする必要はありません。新人さんが特に難しさを感じている場面や、重要な判断が必要なケア、インシデントに繋がりやすい場面などで、意識的に取り入れてみるだけでも効果は大きいですよ。
それに、思考発話は単に「答え」を教えるのとは違います。これは、あくまで「考え方のモデル」を見せること。お手本を知ることで、新人さんは「なるほど、こうやって考えればいいんだ」と、自分で考えるための“足場”を得ることができます。これも、次の秘訣で紹介する「段階的な見守り」にも繋がっていく大切なステップなんです。
この「思考発話」は、新人さんが看護の思考プロセスを体得するための、非常に効果的な指導法だと僕は確信しています。最初はちょっと照れくさいかもしれませんが、ぜひあなたの教え方の引き出しの一つに加えてみてくださいね。
秘訣4:【見守り方】「手→目→心」で段階的に!新人看護師の安全と成長を支える関わり
秘訣の4つ目は、新人さんの成長に合わせた「見守り方」についてです。
前の原則「思考発話」で、ケアやアセスメントの考え方を伝えた後、今度は新人さんが実際に自分でやってみる段階を、僕たち指導者はどうサポートしていけば良いのでしょうか?
『陥りがちな罠』のところ(罠3:過保護指導)でも触れましたが、新人さんに失敗させたくない、安全を守りたい、という気持ちが強すぎて、いつまでも手取り足取り指導を続けていては、残念ながら新人さんはなかなか自立できません。かといって、「じゃあ、一人でやってみて!」といきなり放置してしまうのは、あまりにも無責任ですし、安全面でも大きなリスクがありますよね。
じゃあ、どうすればいいのか?
僕が大切にしているのは、段階的な関わり。つまり、新人さんの習熟度に合わせて、少しずつ任せ方を変えていく見守り方です。
そのイメージとして、僕はよく「手→目→心」という3つのステップを意識しています。これは、子育てにも少し似ているかもしれませんね。新人看護師の安全をしっかりと確保しながら、段階的に自立を促していくための関わり方の目安として参考にしてみてください。
これは、新人さんが基本的な知識や技術を覚え、業務の流れに慣れるまでの最初の段階です。文字通り、手取り足取り、一緒に実践しながら教えます。常にすぐそばにいて、一つひとつの手順を確認し、安全を確保する。そして、「大丈夫?」「ここまでOK?」とこまめに声をかけ、密なコミュニケーションで不安を取り除いてあげる(心も離さない)。まさに、つきっきりでサポートする時期ですね。
基本的なことができるようになってきたら、次のステップ。今度は、新人さん自身に一人でやらせてみる段階です。ここで「手」を離します。ただし! まだ「目」と「心」は離しませんよ。つまり、すぐ近くで見守っていて、危ない時や明らかに困っている時には、すぐに声をかけたり、フォローに入ったりできるようにしておく、ということです。そして、「ちゃんとできてるかな」「困ってないかな」と、常に新人さんの様子を気にかけておく(心は離さない)。
実は、多くの指導者の方がこのステップ2へ移行すること、つまり「手を離す」ことに難しさや怖さを感じるようです(罠3で触れた点ですね)。たしかに「任せる勇気」が必要ですが、ここを乗り越えないと、新人さんの成長は止まってしまいます。
ステップ2を経て、新人さんが自信を持って一人で業務を遂行できるようになったら、最終段階です。今度は、直接的な監視(「目」)も少しずつ減らしていきます。「手」も「目」も離すわけですね。でも、決して「放置」ではありません。ここで大切なのは、「心」は離さない、ということ。つまり、何かあったらいつでも相談できる、頼れる存在であるという 信頼関係 (心の繋がり)は、しっかりと維持し続けるんです。新人さんからの報告・連絡・相談をきちんと受け止め、「いつでも見守っているよ」「困ったらいつでも言ってね」というメッセージを伝え続けることが重要になります。



「じゃあ、いつ『手』を離して、いつ『目』を離せばいいの?」
そのタイミング、悩みますよね。これは、新人さん一人ひとりの 成長 スピードに合わせて、個別に見極める必要があります。焦りは禁物。部署で使っている技術チェックリストや、日々の振り返り、面談などを活用しながら、客観的な評価も交えて判断していくのが良いでしょう。



「それでも、やっぱり任せるのが怖い…」
その気持ち、よく分かります。「罠3」でも触れましたが、「安全に失敗させてあげる」くらいの気持ちも時には必要かもしれません。もちろん、安全管理は徹底した上で患者さんに影響しない失敗を、ですが。そして何より、「先輩がちゃんと見てくれている」「何かあってもフォローしてくれる」という安心感を新人さんに与えること、いつでも相談できる雰囲気を作っておくことが、安全な挑戦を後押しする一番の力になります。
この「手→目→心」という段階的な見守り方。これを意識することで、新人看護師の安全を確保しながら、着実な成長と自立をサポートすることができます。あなたの丁寧な関わり方が、新人さんの未来を明るく照らすと信じて、ぜひ実践してみてください。
秘訣5:【目標設定・計画】成長を促す「指導計画」の作成・共有と活用 方法
秘訣の5つ目は、新人さんの成長をより確実なものにするための、「目標設定」と「指導計画」についてです。
これまでの秘訣で見てきたような丁寧な関わり方をより効果的に、そして計画的に進めていくための、いわば“羅針盤”のようなものですね。



「え、計画なんて立てても、どうせその通りに進まないし…」
「ただでさえ忙しいのに、計画まで作る時間なんて…」
そう思う気持ち、すごくよく分かります。僕も最初はそうでした。でも、闇雲に日々の業務を教えるだけよりも、目指すべきゴール( 目標 )とそこまでの道筋( 計画 )がある方が、指導に一貫性が出て新人さんも僕たち指導者も、ずっと安心して進めるようになるんです。
なぜなら、
- 指導の方向性が明確になる
「今、何を教えるべきか」「次に何を経験してもらうか」が分かりやすくなる。 - 新人さんの安心感に繋がる
「自分は何を期待されているのか」「何を頑張ればいいのか」が具体的に分かり、見通しを持って努力できる。 - 成長が可視化されやすい
「計画に対して、ここまでできるようになったね!」と、進歩を具体的に確認でき、双方のモチベーションに繋がる。
だからこそ、少し手間はかかっても、目標設定と指導計画に取り組む価値は十分にある、と僕は考えています。
では、具体的にどう進めれば良いのでしょうか?
効果的な目標設定のポイント
いきなり大きな目標ではなく、新人さんが「これなら頑張れそう!」と思えるような、具体的で分かりやすい目標設定が大切です。
例えば、「立派な看護師になる」ではなく、「3ヶ月後までに、〇〇(例:Aさんの受け持ち患者の情報収集)を、先輩のサポートなしで一人でできるようになる」といったように、誰が見ても何を達成すれば良いか分かるレベルで具体的にします。
これがすごく大事! 指導者が一方的に決めるのではなく、「〇〇さんは、まずは何ができるようになりたい?」「3ヶ月後、どんなことができるようになっていたいかな?」と、新人さんの意向も聞きながら一緒に決めることで、目標達成への主体性がぐっと高まります。
高すぎる目標は、「どうせ無理だ…」と意欲を削いでしまいます。かといって簡単すぎても成長に繋がりません。新人さんの現在のレベルを見極めて、「少し頑張れば手が届く」くらいの、ストレッチの効いた目標設定を心がけましょう。
「いつまでに」という期限を設けることで、目標達成に向けた具体的な行動計画が立てやすくなります。まずは1ヶ月、次は3ヶ月、といった短期・中期の目標を設定するのがおすすめです。
指導計画の作成と要素
目標が決まったら、それを達成するための具体的な指導計画を立てていきます。
難しく考えなくてOK!シンプルなもので大丈夫
「計画書」というと身構えてしまうかもしれませんが、完璧を目指す必要はありません。箇条書きのメモ程度でも、ポイントが押さえられていれば十分です。大切なのは「作ること」よりも「活用すること」ですからね。
- いつまでに(期間)
- 何ができるようになるか(到達目標)
- そのために何を経験するか(具体的な指導内容・経験項目)
- どうやって指導するか(指導方法:OJT中心か、研修参加か、自己学習課題か等)
- 誰が主に関わるか(担当者:プリセプターか、チーム全体か等)
- どうやって達成度を確認するか(評価方法・時期:チェックリスト、面談、レポート等)
部署のフォーマットやガイドラインも参考に
多くの病院や部署では、新人教育用の指導計画フォーマットや年間スケジュール、チェックリストなどが用意されているはずです。まずはそれらを活用しましょう。
計画の「共有」と「活用」が鍵!
計画は、作って終わりでは意味がありません。新人さんと共有し、日々の指導や評価に活用してこそ、その力が発揮されます。
「これから一緒に、この計画に沿って進めていこうね」「目標達成できるようにサポートするからね」と伝え、計画書自体を新人さんにも渡して、いつでも確認できるようにしておくのがおすすめです。
週に一度、あるいは月に一度でも良いので、「計画に対して、今どのくらい進んでるかな?」「順調なこと、逆に難しいと感じることはある?」など、計画を基に一緒に進捗を確認し、対話する時間を持ちましょう。これが次の原則「フィードバック」にも繋がっていきます。
「計画通りに進まない…」そんな時ももちろんあります。新人さんの成長ペースは一人ひとり違いますし、予期せぬ出来事も起こるでしょう。計画はあくまで目安と考え、状況に合わせて柔軟に目標やスケジュールを見直していくことが大切です。その際も、変更点をしっかり新人さんと共有することを忘れずに。



「計画作りって、やっぱり大変そう…」
そうですよね。でも、一度ベースを作ってしまえば、次年度以降はそれを修正して使えますし、何よりその後の指導が格段に進めやすくなるメリットは大きいです。最初は簡単なメモからでも大丈夫。部署の先輩の計画を参考にさせてもらったり、チーム内で協力して作成したりするのも良い方法だと思いますよ。
適切な目標設定と、それを達成するための指導計画の作成・共有・活用。
これは、新人さんの着実な成長を促すための、そして僕たち指導者にとっても心強い道しるべになります。ぜひ、あなたの指導に取り入れてみてくださいね。
秘訣6:【フィードバック】具体的な行動への承認で自信と意欲を高める
秘訣の6つ目は、新人さんの成長をグンと加速させるためのとても重要な関わり、「フィードバック」についてです。
前の秘訣で触れた「計画に基づいた振り返り」の場面でも、このフィードバックは欠かせません。
「フィードバック」というと、なんだか「評価される」とか「ダメ出しされる」みたいで、ちょっと身構えてしまう…なんてイメージ、ありませんか? 新人さんだけでなく、もしかしたら僕たち指導する側も、少し苦手意識を持っているかもしれません。
でも、本来フィードバックは、新人さんの成長をサポートするための大切な「情報提供」なんです。自分の行動が周りからどう見えているのか、どんな影響を与えているのか、それを具体的に知ることで、新人さんは、
- 自分の行動を客観的に振り返ることができる
- できたことへの自信を深めることができる
- 次に何を頑張れば良いかが明確になり、意欲を高めることができる
という、成長に繋がるたくさんのメリットを得られます。
特に新人指導において、僕が効果的だと強く感じているのは、「承認」を中心としたポジティブなフィードバックです。「秘訣1」で紹介した「4つの承認」(存在・行動・成果・成長)を、このフィードバックの場面でこそ、意識的に活用してほしいんです。
なぜなら、「できていること」「頑張っていること」を 具体 的に認めてもらう経験こそが、新人さんの「自分ならできるかも!」という“ 自信 ”と、「もっと頑張ろう!」という“ 意欲 ”を何よりも強く引き出してくれるからです。
では、自信と意欲を高める効果的なフィードバックを行うために、どんなことを心がければ良いのでしょうか? いくつかポイントを挙げてみます。
良い行動があった時、あるいは改善が必要な行動があった時、できるだけ時間が経たないうちに伝えるのが効果的です。記憶が新しいうちの方が、具体的な場面と結びつけて振り返りやすいですからね。ただし、人前(特に患者さんの前)で指摘するなど、伝える場所やタイミングへの配慮は必要ですよ!
「良かったよ」「頑張ったね」だけでは、何がどう良かったのか伝わりません。「さっきの〇〇さん(患者さん)への声かけ、すごく丁寧で分かりやすかったよ。おかげで患者さんも安心した表情だったね」というように、いつ、どんな行動が、どう良かったのか、そしてどんな影響があったのかを具体的に伝えましょう。
フィードバックは、人格を評価するものではありません。「あなたは覚えが悪いね」ではなく、「この手順を覚えるのに、少し時間がかかっているみたいだね。どこが特に難しく感じる?」というように、あくまで客観的な「 行動 」や「事実」に焦点を当てて話すことが大切です。
「当たり前」と思えるようなことでも、意識して探せば、承認できるポイントはたくさんあるはず。挨拶がしっかりできた、時間通りに準備ができた、自分から質問してくれた、患者さんに笑顔で対応できた…。小さな「できた!」を見逃さず、言葉にして伝える。この積み重ねが、新人さんの自信を育みます。
もちろん、時には改善が必要な点を伝えることも大切です。その際は、まず「〇〇はしっかりできていたね」とできたこと(承認)を伝えた上で(いわゆるサンドイッチ型フィードバックも有効ですね)、「ただ、△△の部分は、こうするともっと良くなると思うよ」と伝えるのが基本です。
ポイント5の補足(IメッセージとYouメッセージ)
ここで多くの指導者さんが悩むのが、



「言いにくいことを伝えたら、『怒られた』って思われないかな…」
「指摘することで、関係が悪くならないかな…」
ということではないでしょうか。
そんな時に、ぜひ意識してほしいのが、「I(アイ)メッセージ」で伝える、というコミュニケーションの方法です。
僕たちはつい、「あなた(You)は〇〇ができていない!」「あなた(You)の報告は遅い!」というように、「あなた」を主語にして、相手の行動を直接的に指摘してしまいがちです(これをYouメッセージと言います)。ストレートで分かりやすいかもしれませんが、言われた方は「責められた」「否定された」と感じて、心を閉ざしてしまう可能性が高いんです。
そうではなくて、「私(I)」を主語にする。



「私(I)は、〇〇してもらえると嬉しいな/助かるな」
「私(I)は、〇〇だと少し心配になるんだ」
「私(I)は、〇〇だとこう思うんだけど、どうかな?」
というように、自分の気持ちや期待、考え、あるいは提案として伝えるのが「Iメッセージ」です。
例えば、報告が遅れがちな新人さんに伝える場合…
あるいは、手順の確認が必要な場合…
Iメッセージの方が、相手への非難がましくなく、こちらの気持ちや状況が伝わりやすいと思いませんか? あくまで「私」の意見や感情として伝えることで、相手も冷静に受け止めやすくなり、建設的な対話に繋がりやすくなるんです。
このように、改善点を伝える際には、具体的な行動への指摘に加えて、Iメッセージを意識する。そして、「どうすれば良くなるか」という具体的な改善策や期待を一緒に伝える。「〇〇は良かったけど、△△はこうするともっと良くなると思うよ。一緒にやってみようか」という形で締めくくれると、さらに前向きなフィードバックになりますよ。
秘訣7:【自己成長】指導者も学び続ける!研修や文献でスキルアップ
さて、いよいよ7つの秘訣の最後になりました。最後にお伝えしたいのは、他の誰でもない「指導者」であるあなた自身の「自己成長」についてです。



「え、新人指導の話なのに、自分の成長?」
そう思う人もいるかもしれませんね。でも、効果的な指導を提供し続けるためには、僕たち指導者自身が学び続ける 姿勢を持つことが、実はとっても大切なんです。
なぜなら、新人指導は、決して「教えるだけ」の一方的なものではないから。
新人さんからの素朴な疑問に答えようとすることで、自分自身の知識があやふやだったことに気づかされたり、分かりやすく伝えようと工夫する中で、看護観が深まったり…。新人さんの多様な考え方や価値観に触れることで、自分の視野が広がることだってたくさんあります。まさに「教えることは学ぶこと(教学相長)」なんですよね。新人指導は、僕たち指導者にとっても、かけがえのない自己成長の機会なんです。



でもそれに気づいてない人も多いんですよね…。
実際、僕も指導者の子に「新人を指導することであなたも学ぶことがあるはずだよ」と伝えたら「???」って顔をされた経験があります。
看護の知識や技術、医療を取り巻く環境、そして新人さんの気質だって、時代と共にどんどん変化していきます。僕たちが新人だった頃の「常識」が、今では通用しないなんてことも少なくありません。だからこそ、過去の経験だけに頼るのではなく、常に新しい知識やスキルを学び続けることが、指導の質を保ち、向上させていく上で不可欠なんです。
そして何より、指導者が学び続ける 姿は、新人さんにとって最高のロールモデルになります。「先輩も頑張ってるんだな」「私ももっと学ばなきゃ!」と、自然と前向きな意欲を引き出すことに繋がるはずです。
じゃあ、具体的にどうやってスキルアップしていけば良いのでしょうか? 難しく考える必要はありません。
これが一番身近で重要な学びの場。「今日の新人さんへの関わり、どうだったかな?」「もっと分かりやすい伝え方はなかったかな?」と、意識的に自分の指導を振り返る習慣を持つことが大切です。新人さんの反応や表情も、貴重な学びのヒントになります。
もし機会があれば、院内・院外で開催される研修プログラムに参加してみましょう。プリセプター研修、コミュニケーション研修、リーダーシップ研修など、様々なテーマがあります。僕自身も、実習指導者講習会や認定看護管理者の研修などで、たくさんの知識や刺激を得ることができました。他の施設の指導者と交流できるのも良い経験になりますよ!
看護教育やコーチング、コミュニケーションに関する文献や専門書を読んでみるのもおすすめです。最近は、指導に役立つ分かりやすい書籍もたくさん出ていますし、看護系の雑誌で特集が組まれることもあります。通勤時間や休憩時間など、短い時間でもインプットは可能です。
一人で抱え込まずに、同じように指導を担当している同僚や経験豊富な先輩に、「〇〇さんって、どうやって指導してる?」「こんな時、どうしてる?」と気軽に相談したり、情報交換したりするのも、とても有効な学びの場です。お互いの悩みや工夫を共有することで、新たな気づきや解決策が見つかることも多いですよ!



「もうベテランだし、今さら学ぶことなんて…」
そんなことは絶対にありません! 看護も指導法も、日々進化しています。あなたの豊富な経験に新しい知識や視点が加われば、指導はさらに深みを増すはずです。



「忙しくて、なかなか学ぶ時間が取れないんだよね…」
その気持ちもよく分かります。でも、例えば、丸一日かかる研修に参加できなくても、オンラインで短時間で学べるものや、スマホで読める記事、同僚との5分間の情報交換だって、立派なスキルアップに繋がります。大切なのは「学び続けよう」という意識を持つことだと、僕は思います。
指導者自身が学び続けることで、指導の引き出しが増え、それは必ずあなたの自信にも繋がります。そして、その成長する姿がきっと新人さんの心にも響くはず。
新人さんと共に自己成長していく。そんな素敵な指導者を目指して、日々の小さな「学び」を大切にしていきましょう。
【Q&A】忙しいプリセプターのよくある悩みとヒント
7つの秘訣、お疲れ様でした!ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
秘訣を意識するだけでも、きっとあなたの新人指導は変わっていくはずです。



とはいえ…、日々の指導の中では、秘訣だけでは解決しきれないもっと具体的な悩みもたくさん出てきますよね。
僕もいまだに日々、いろんな壁にぶつかっています(笑)。
そこで、ここからは【Q&A】形式で、特に忙しいプリセプターの皆さんが抱くであろう悩みについて、僕なりのヒントや考えをお伝えしていきます。
少しでも、あなたの悩みが軽くなるきっかけになれば嬉しいです。
Q1. どうしても指導の時間が取れない時はどうすれば?
A: これは本当に、指導者にとって永遠の課題です…。僕も、そもそも業務が忙しすぎてそれどころじゃない、って日はよくあります。まず大切なのは、「完璧な指導をしよう!」と気負いすぎないことかもしれません。限られた時間の中で、できる工夫を少しずつ試してみてはどうでしょうか?
- 「5分だけ振り返り」を日課にする
長時間確保できなくても、1日の終わりに5分だけ、「今日できたこと」「困ったこと」を共有する時間を作るだけでも効果があります。 - 指導内容を絞る
「今日はこれだけは必ず伝えよう/一緒にやろう」と、その日の目標を一つか二つに絞る。欲張らないことも大切です。 - 口頭+αの工夫
口頭での説明に加えて、簡単な手順メモを渡したり、チェックリストを活用したりするのも、時間の節約になります。 - チームで協力する
一人で抱え込むのはNG!「今日は〇〇さんのこの部分を見ておいてもらえませんか?」と、チームのメンバーに協力をお願いするのも、とても大切なことです。 - スキマ時間の活用
通勤時間や休憩中に、指導に関する本を読んだり、この記事のようなWeb記事をチェックしたりするのも、立派なインプットです(秘訣7参照)。
Q2. 新人さんのタイプ別(反応が薄い、質問が多い/少ない等)の関わり方のコツは?
A: これも、よくある悩みですよね。新人さんだって、一人ひとり性格も違えば経験も違う。だから、関わり方に「絶対の正解」はないんですが、僕が考えるタイプ別の傾向と考えられる背景、そして関わりのヒントを少しお伝えしますね。
| タイプ | 考えられる背景・特徴 | 関わりのヒント(対応策) |
|---|---|---|
| 反応が薄いタイプ | ・緊張や不安が強い ・感情や考えをうまく表現できない | ・まずは安心できる雰囲気づくり(秘訣1)、存在承認を心がける ・「はい/いいえ」で答えやすい質問や、具体的な行動について聞くことから始めてみる(例:「〇〇はできた?」) |
| 質問が少ないタイプ | ・遠慮している ・質問するタイミングを逃している ・「こんなこと聞いていいのかな」と思っている ・実は理解していない(分かったふり) | ・「いつでも、どんなことでも聞いていいんだよ」と繰り返し伝える ・質問しやすいタイミングを作る(例:業務が落ち着いた時、一対一の時) ・理解度を確認する問いかけも行う(例:「〇〇について、自分の言葉で説明してみてくれる?」) ・こちらから「何か困ってることない?」と具体的に聞いてみる |
| 質問が多いタイプ | ・知りたい!という意欲が高い ・不安感が強く、一つひとつ確認しないと進めない ・自分で考える前にすぐ聞いてしまう | ・まずは意欲の表れと前向きに受け止める ・自分で考える時間も促す(秘訣2の発問を活用:「〇〇さんはどう思う?」「まず自分で調べてみようか?」) ・調べる方法(マニュアルの場所、手順書の確認方法など)を具体的に教える ・質問の意図を確認する(不安からか、純粋な疑問か) |
大切なのは、決めつけずに、まず「この子はどうしてこういう反応なのかな?」と相手の背景を想像してみることですね。
Q3. 最近の新人さん(いわゆるZ世代)とのコミュニケーションで気をつけることは?
A: 「Z世代」という言葉、よく耳にしますよね。僕も、若いスタッフとの関わりで意識することはあります。ただ、大前提として、「〇〇世代だからこうだ!」と一括りにするのは危険だと僕は思っています。あくまで個人差が大きい、ということを忘れないようにしたいですね。
その上で、一般的に言われる「Z世代」の傾向として、
- デジタルネイティブ: 情報収集が得意。オンラインでのコミュニケーションに慣れている。
- 効率・合理性重視: 無駄を嫌う傾向。指示の背景や理由(なぜそれが必要か)を説明すると納得しやすい(秘訣3の思考発話が有効)。
- 承認欲求が高い: 自分の頑張りや成果を認めてほしい気持ちが強い(秘訣1の承認が響きやすい)。プロセスも評価されることを好む。
- プライベート重視: ワークライフバランスを大切にする。時間外の連絡や過度な干渉は避けた方が良い場合も。
- ハラスメントへの意識が高い: 言葉遣いや態度には、これまで以上に注意が必要。
といった点が挙げられるかもしれません。これらの傾向を頭の片隅に置きつつも、目の前の新人さん個人としっかり向き合い、対話を重ねていくこと(秘訣1)が、結局は一番大切だと僕は考えています。
Q4. 新人指導の参考になる本・文献・研修プログラムは?
A: 学び続けようという姿勢は常に持っておきたいですね(秘訣7)! 世の中には、指導に役立つ情報がたくさんありますよ。
- 書籍: 書店に行けば、「看護教育」「新人指導」「プリセプター」「コーチング」「コミュニケーション」「フィードバック」といったキーワードで、たくさんの本が見つかります。まずは、タイトルや目次を見て「これなら読めそう!」と感じるものから手に取ってみては?
- 文献: 看護系の学会誌や専門誌(例えば『看護教育』や『看護管理』など)には、新人指導に関する特集や研究論文が掲載されていることがあります。少し専門的になりますが、深く学びたい人にはおすすめです。大学図書館や医中誌Web、CiNiiなどで探せます。
- 研修プログラム: 院内で開催されるプリセプター研修やリーダーシップ研修はもちろん、看護協会や外部の企業が主催するセミナー、オンライン研修などもたくさんあります。僕が受けた実習指導者講習会も看護協会が開催しています。実習指導と名前はついていますが、教育について多くの学びを得ることができますよ!
- Webサイト・ブログ: 僕のこのサイトのように、現役の看護師や指導経験者が発信している情報も、実践的なヒントが得られて参考になると思いますよ。(信頼できる情報か見極めは必要ですが)
たくさんの情報に触れることも大切ですが、まずは一つでも「これは!」と思うものを見つけて、実践してみることが成長への近道だと思います。



よくある悩みへのヒント、少しは参考になったでしょうか?
悩みは尽きないものですが、一人で抱え込まず、情報収集したり、周りの同僚や先輩に相談したりしながら、あなたらしい関わり方を見つけていってくださいね。
まとめ:自信を持って、新人看護師と共に成長するやりがいのある指導へ
ここまでお伝えしてきた大切なポイントを振り返りましょう。
新人看護師の指導がなぜ難しいのか、その理由から始まり、僕たちがつい陥ってしまいがちな「5つの罠」、そして、その壁を乗り越え、新人さんの成長と主体性を引き出すための「7つの秘訣」について、具体的な方法や考え方を紹介してきました。
もう一度、7つの秘訣を思い出してみましょう。
- 【信頼関係】:何よりもまず、心理的安全性を土台に関係を築く(承認・傾聴)
- 【質問力】:詰問ではなく「発問」で思考力を育む
- 【教え方】:思考プロセスを見せる「思考発話」で理解を促す
- 【見守り方】:「手→目→心」で段階的に安全と成長を支える
- 【目標設定・計画】:指導計画を作成・共有し、成長を可視化する
- 【フィードバック】:具体的な行動への承認で自信と意欲を高める
- 【自己成長】:指導者自身も学び続け、共に成長する
たくさんの秘訣があって、「全部やるのは大変そう…」と感じたかもしれませんね。でも、最初から完璧にこなす必要なんて全くありません。
この中で僕が特に、そして繰り返しお伝えしたいのは、全ての土台となるのは「秘訣1:信頼関係」であるということです。技術や知識を教える前に、まずは目の前の新人さんと人としてしっかり向き合い、安心できる関係性を築くこと。ここが、やりがいのある指導への一番大切なスタートラインだと僕は感じています。
そして、新人指導は決して「教える」だけの一方通行ではありません。新人さんのひたむきな姿や、思いがけない視点から、僕たち指導者自身が学ぶことも本当にたくさんあります。まさに「共に成長」していく、尊いプロセスなんですよね。
新人指導は、たしかに大変です。悩むことも、落ち込むこともあるでしょう。でも、この記事でお伝えしたヒントが、あなたの自信に繋がり少しでも肩の荷を下ろすお手伝いができたなら、とても嬉しく思います。



焦らず、気負わず、あなたらしいペースで。
ぜひ、ここで見つけたヒントを一つでも二つでも、明日の新人看護師との関わりに活かしてみてください。
そして、試行錯誤しながら、あなた自身のやりがいのある指導の形を見つけていってくださいね。
僕も、まだまだ試行錯誤の連続です。一緒に頑張っていきましょう!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
あなたの看護と指導が、より一層輝くことを心から願っています。

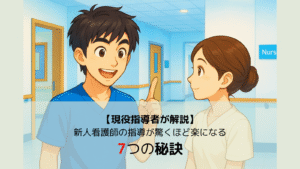
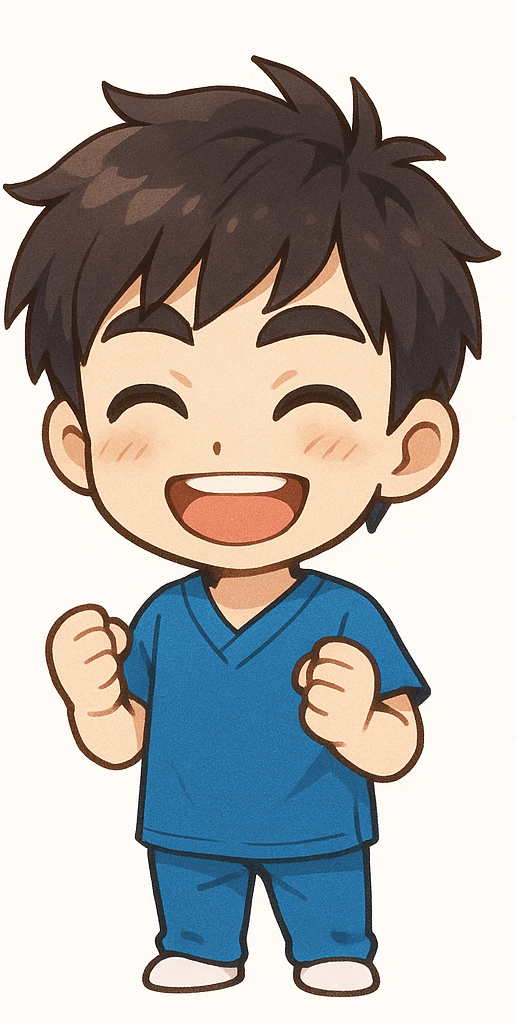
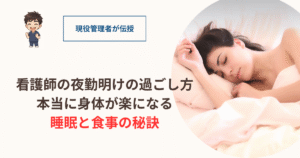

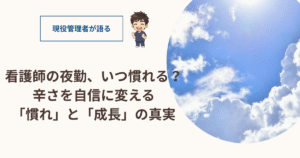
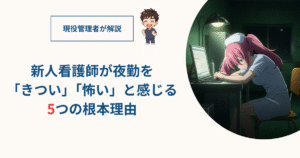
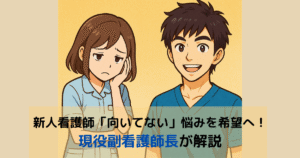
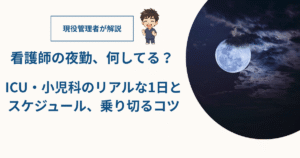


コメント